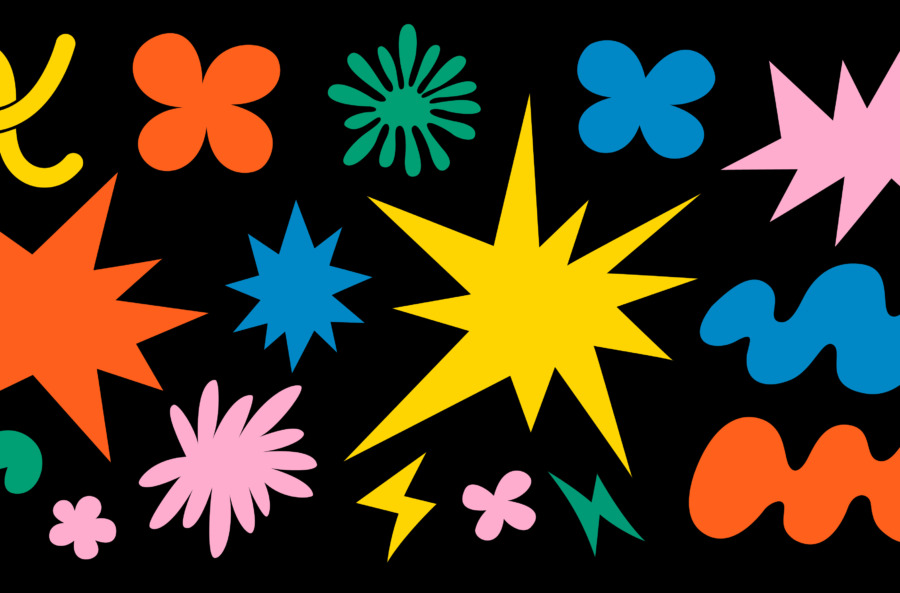近年、多くの有名企業やブランドがロゴの書体をサンセリフ体(ゴシック体、いわゆる「ひげ飾り」のないフォント)に変更する動きが目立っています。例えばGoogleはカラフルなセリフ体ロゴからシンプルなサンセリフ体ロゴへ、老舗ファッションブランドのバーバリーも伝統的なロゴを刷新してモダンなサンセリフ体にするなど、大きな転換が相次ぎました。
こうした「ロゴのサンセリフ体化」の現象は、単なる一過性のブームなのでしょうか?それともデザインの持続的な進化の一部と言えるのでしょうか? この記事では、その背景や歴史、心理的効果、過去の流行の揺り戻し、具体的なブランド事例、そして今後の予測についてご紹介します。
サンセリフ体が好まれる背景

まず、なぜ今サンセリフ体のロゴが好まれているのか、その背景を探ってみましょう。大きな要因の一つにデジタル時代への適応があります。現代ではスマートフォンやパソコンなど小さな画面でロゴを見る機会が増えました。セリフ(飾り線)のある従来のフォントだと、画面が小さい場合に細部がつぶれて判別しにくくなることがあります。その点、装飾のないサンセリフ体はシンプルな線で構成されているため、小さなサイズでも読みやすく、低解像度のスクリーンでも鮮明さを保ちやすいのです。事実、多くの企業がロゴ変更の理由に「デジタルでの視認性向上」を挙げています。
次に挙げられるのがモダンな美意識への適合です。セリフ体の文字は伝統的で格式高い印象を与える一方、今日の若い世代やテクノロジー志向の消費者は「シンプルで現代的」なデザインを好む傾向があります。サンセリフ体のロゴは無駄をそぎ落とした洗練された雰囲気で、革新性や先進的なイメージを伝えるため、特にデジタル世代の心に響きやすいと言われます
従来のセリフ体ロゴが「伝統」や「格式」を象徴していたとすれば、サンセリフ体ロゴは「革新」や「親しみやすさ」の象徴と見ることができます。
また、グローバルな視点での汎用性も背景にあります。セリフ体の書体デザインには欧米の歴史や文化的文脈が色濃く反映されていることが多いですが、サンセリフ体は装飾が少ない分ニュートラル(中立)的で、言語や文化を超えて受け入れられやすいとされています。世界中でビジネスを展開するブランドにとって、どの国の消費者が見ても違和感の少ないフォントでロゴを統一できるメリットは大きいでしょう。

さらに無視できないのがミニマリズム(最小限主義)のトレンドです。昨今のデザイン全般に言えることですが、ファッションやインテリアなど幅広い分野で「シンプルで飾らない美」が支持を集めています。ロゴデザインも例外ではなく、「Less is More(より少ないことはより豊かなこと)」の精神が浸透した結果、余計な装飾を排したサンセリフ体のロゴは時代の空気に合致すると考えられているのです。凝った装飾や派手さよりも、情報が一瞬で伝わるクリアさや余白の美しさが重視されるようになりました。
以上のように、デジタル対応の実用面から文化・美意識の変化まで、様々な背景が重なってサンセリフ体ロゴの流行を後押ししています。この流れは単なる偶然ではなく、現代の社会・技術環境に適応した結果と言えるでしょう。
タイポグラフィとロゴデザインの歴史的変遷

現在のサンセリフ体ブームを理解するには、タイポグラフィ(書体デザイン)の歴史やロゴデザインの流れを振り返ることも有益です。実はセリフ(ひげ飾り)のないサンセリフ書体自体は19世紀初頭には既に登場していました(1800年代にイギリスのウィリアム・キャズロン4世が世界初のサンセリフ活字を作ったと言われます)。しかし長らく印刷物の本文などにはセリフ体が主流で、サンセリフ体が広く普及するのはもう少し後の時代です。
20世紀に入ると、モダニズムデザインの潮流の中でサンセリフ体が脚光を浴びます。特に1950年代以降、Helvetica(ヘルベチカ)やUnivers(ユニバース)といった新しいサンセリフ体フォントが次々と生み出され、シンプルで機能的な美を体現する書体としてもてはやされました。この頃、多くの企業がロゴにサンセリフ体を採用し始め、サンセリフ=現代的で先進的というイメージが定着していきます。
しかしデザインの流行は常に一方向ではなく循環的です。モダニズムへの反動から、1980年代~90年代初頭には再びセリフ体の持つクラシックな品格が見直され、企業ブランディングでセリフ体が主流となる時期もありました。このように、ある時代にはサンセリフ体が新鮮に映り、また別の時代には「やはり伝統回帰を」とセリフ体が復権する、といった具合に振り子が揺れ動いてきたのです。
書体の専門家リック・バンクス氏は「クリエイティブなものは全て循環するものです」と述べ、1950年代のサンセリフ黄金期(HelveticaやUniversなど)から、その反動で80年代〜90年代にセリフ体が復興した歴史に言及しています。この言葉が示すように、タイポグラフィの世界では常に新旧のバランスを取る動きが繰り返されてきました。
ロゴデザインも同様で、企業やブランドのロゴは時代のデザイン潮流を映す鏡です。1900年代初頭のロゴには凝った紋章や筆記体(スクリプト体)が多く見られましたが、戦後は工業的で整然としたサンセリフ体ロゴが増え、1990年代〜2000年代には一部でグラデーションや立体感のあるロゴ(Appleの虹色ロゴや3D風ロゴなど)が流行した時期もありました。そして2010年代に入るとフラットデザインやミニマルデザインの流れとともにロゴも極力シンプルに、文字も飾りのないサンセリフ体へ……という現在の傾向が強まったのです。
このような歴史的変遷を踏まえると、今起きているサンセリフ体化も決して孤立した現象ではなく、過去から続くデザインの振り子運動の一環として理解できます。では、なぜ現在これほど多くのブランドがサンセリフ体を選ぶのか、その心理的な効果にも注目してみましょう。
サンセリフ体が与える印象と心理的効果

書体は見る人に様々な心理的印象を与えますが、サンセリフ体のロゴにはどんなイメージ効果があるのでしょうか。まず指摘されるのは、やはり「シンプルで現代的」という印象です。先述の通りサンセリフ体は装飾がなく直線的・幾何学的な形状を持つため、洗練されていて時代に合った雰囲気を醸し出します。特にテクノロジー企業などでは「革新的・先進的」「ミニマルでクリーン」というブランドイメージを打ち出すのにうってつけであり、実際にIT業界の巨頭であるGoogleやYahoo!はロゴからセリフ体を完全に排除してシンプル路線に舵を切りました。
また、サンセリフ体はニュートラル(中立)で柔軟なイメージを与えるとも言われます。Monotype社の書体デザイナー、フアン・ビジャヌエバ氏は
「サンセリフ体は今やブランドデザインにおける無難で安全な選択肢となっており、ニュートラル(癖がなく中立的)でシンプル、俊敏といった意味合いを帯びている」
と述べています。要するに、大きくハズす心配がなく時代遅れにも見えにくい、汎用性の高い安心できるスタイルというわけですね。
一方で、視認性・可読性の高さもサンセリフ体ロゴの大きな強みです。特に小さなサイズで表示される場合やデジタル画面での閲覧では、前述の通りサンセリフ体の方が判読しやすい傾向があります。ユーザーにパッと見てブランド名を認識してもらうには、複雑な書体よりシンプルな書体の方が効果的です。読みやすさは心理的な負担の軽減にもつながり、結果として「このブランドは分かりやすく開かれている」というポジティブな印象を持ってもらえる可能性があります。
サンセリフ体ロゴが与えるイメージをまとめると、「現代的・革新的」「シンプルで親しみやすい」「ニュートラルで幅広い層に受け入れられる」「視認性が高く安心感がある」といったところでしょうか。もちろん書体だけですべてが決まるわけではありませんが、ロゴというブランドの「顔」においてサンセリフ体を使うことは、そうした心理的メッセージを発信することにつながります。
なお逆にセリフ体には「伝統的・格式高い」「権威や信頼感がある」というプラスのイメージもあります。歴史ある新聞のロゴや高級ブランドのタイポグラフィにはセリフ体が用いられ、「由緒正しさ」や「高級感」を演出してきました。サンセリフ体への変更は、そうした従来のブランド資産である信頼感や伝統を捨てるリスクも伴います。この点については後述の「デザインの揺り戻し」の中で再び触れてみましょう。
デザイントレンドの循環と「揺り戻し」の可能性

前述のように、デザインの流行はしばしば循環する(繰り返す)ものです。今まさに主流となっているサンセリフ体ブームも、永遠に続くとは限りません。実際、ここ数年の間に早くも「サンセリフ体一辺倒の風潮」に対する反動や個性回帰の兆しも見えてきています。
デザイン界ではこの現象を指して「振り子が逆に振れ始めている」と表現する人もいます。2024年のAlex Harper氏の記事は、「シンプルさを追求する潮流の一方で、いずれ懐古や個性志向の高まりとともに再びセリフ体の魅力が再発見されるかもしれない」と述べています。
また別の専門家は「皆が同じようなロゴに気づき始め、何か違うものを求めるようになっている」とも指摘しています。確かに多くのブランドがこぞって似たようなサンセリフ体ロゴになると、消費者から見れば差別化が難しく「どれも同じに見える」状態になりかねません。そのため敢えて他と違う個性を出すために、あえてセリフ体やユニークな書体を採用し直すブランドも出てきているのです。

・Saint Laurentのロゴ / vli86 – stock.adobe.com
実例を挙げましょう。2018年前後から高級ファッションブランド各社が一斉にロゴをサンセリフ体のシンプルなデザインに変更しました。サンローラン(Yves Saint Laurent)がブランド名ロゴを細身のサンセリフ体に改めたのを皮切りに、バレンシアガ、バルマン、ベルルッティなど多くのラグジュアリーブランドが似たような幾何学的サンセリフ体ロゴに乗り換え、「みんな同じようなロゴだ」と揶揄される事態にもなりました。これはブランドのアイデンティティが薄れ、“無難すぎて没個性”とも言われる「ブランディングの画一化」への批判を生みました。
wake up babe new logo trend just dropped pic.twitter.com/LRcNPxj2vr
— Joseph Alessio (@alessio_joseph) February 6, 2023
ところが2023年、バーバリー(Burberry)が大胆にもクラシックな紋章ロゴを復活させたのです。バーバリーは2018年に創業当初から百年以上使っていた騎士と馬のエンブレム付きセリフ体ロゴを廃し、極めてシンプルなサンセリフ体のロゴ(モノグラム)へと刷新していました。これは当時の「モダンでミニマル」路線を象徴する決断でした。しかし新たにクリエイティブ・ディレクターに就任したデザイナーは伝統回帰を選び、2023年には騎士と馬のエンブレムを復刻させた新ロゴを発表しました。新ロゴの書体もクラシカルなセリフ体で、バーバリーが本来持つ英国的伝統と気品を再び前面に押し出すデザインとなっています。この動きは「ついに高級ブランド界もサンセリフ至上主義から脱却か?」と話題を呼び、「ミニマルなサンセリフロゴ時代の終焉かもしれない」との声も上がりました。

・チョバーニ(Chobani)のロゴ / MelissaMN – stock.adobe.com
バーバリー以外にも、2018年にサンセリフ体のロゴから可愛いセリフ体ロゴへ切り替えたヨーグルトブランドのチョバーニ(Chobani)や、2017年にブログプラットフォームのMediumが伝統的な新聞社を思わせるセリフ書体に変更した例など、セリフ体復権の動きが徐々に見られます。これらは「ノスタルジー(郷愁)」「人間味・温かみ」を再評価する動きとも関連しており、デジタル全盛だからこそ逆にレトロで味わいのある書体で他社との差別化を図る狙いがあります。Monotype社のレポートでも「長年サンセリフ一色だった反動で、字体に個性と魅力を取り戻す手段としてセリフ体が再注目されている」と分析されています。
以上のように、サンセリフ体ブームに対する揺り戻しは確かに起き始めています。ただし、これは直ちにサンセリフ体が廃れるという意味ではありません。むしろデザインの多様化が進んでいると捉えるべきでしょう。次章では、実際にロゴを変更した主要ブランドの事例を見つつ、その狙いを確認してみます。
主要ブランドのロゴ変更事例とその意図

・Googleのロゴ / TOimages – stock.adobe.com
ここで、実際にサンセリフ体ロゴへ変更した(あるいは再び別スタイルに戻した)主要ブランドの事例をいくつか見てみましょう。それぞれのブランドがどんな意図でロゴを変更したのかを知ると、先述の流行の背景や揺り戻しの流れが具体的に理解できます。
Google(グーグル) – 2015年にセリフ体からサンセリフ体へ転換
世界最大の検索エンジンであるGoogleは、2015年にロゴの書体を大きく刷新しました。それまで使用していた「筆記体風のセリフ体ロゴ」から、カラフルで丸みを帯びたサンセリフ体ロゴへ変更したのです。この変更の理由についてGoogleは「モバイルなどあらゆるプラットフォームで読みやすく表示できるようにするため」と説明しています。
新ロゴはシンプルな幾何学的サンセリフ体で、小さなスマホ画面でも視認性が高く、アイコンなどにも展開しやすいデザインになりました。同時に親しみやすさや遊び心も感じさせるフォントで、「誰にでも使いやすい先進的なサービス」というGoogleのブランドイメージを体現しています。
Burberry(バーバリー) – 2018年に伝統ロゴをサンセリフ体に刷新、2023年に再び伝統回帰
前章でも触れた英国の老舗ファッションブランド、バーバリーのケースです。2018年、バーバリーは創業以来守ってきた騎士の紋章とセリフ体ロゴを廃止し、大胆にもモダンなサンセリフ体ロゴへ変更しました。この新ロゴは黒字のシンプルなサンセリフ体で、「伝統から未来へ踏み出す決意」の表れとも受け取られました。当時は他の多くの高級ブランドも同様のミニマル路線を取っており、バーバリーもその流れに乗った形です。
しかしその5年後の2023年、バーバリーは再び方向転換します。新任デザイナーのもと、ブランドのヘリテージ(遺産)を重視する戦略に切り替え、騎士と馬のエンブレムおよびクラシックなセリフ体のロゴを復活させたのです。この決断には「ブランドの原点を再確認し差別化を図る」狙いがありました。他社と似通ってしまったロゴをやめ、伝統あるバーバリーらしさを取り戻すことで、高級ブランドとしての格を再度明確に示そうとしたのです。
BMW(ビー・エム・ダブリュー) – 2020年にフラットデザインのサンセリフ体ロゴに
ドイツの自動車メーカーBMWもロゴをアップデートした企業の一つです。BMWの伝統的ロゴといえば青と白の円盤(プロペラを想起させる意匠)に社名の頭文字「BMW」が載ったデザインですが、2020年にそのロゴが大幅にリニューアルされました。具体的には、長らく使われてきた黒い円枠と立体的な光沢を廃し、透明な円枠と平面的な2Dデザインに変更、文字もほっそりとしたサンセリフ体になりました。この新ロゴについてBMWは「オープンさと明快さを表現し、デジタル時代に適したもの」と説明しています。
フラットで洗練されたデザインはウェブサイトやSNSアイコンなどデジタル媒体との相性が良く、時代に即したアップデートと言えるでしょう。「未来のモビリティを象徴する」という意気込みが込められたこのロゴからは、伝統あるメーカーが現代的感性とユーザーとのより密接な関係性を重視し始めたことがうかがえます。
以上のように、各ブランドがロゴを書体から刷新する際にはそれぞれ明確な意図や背景があります。Googleはデジタル時代のユニバーサルさを選び、バーバリーは一度モダン化した後に原点回帰で差別化を図り、BMWは未来志向とデジタル対応を打ち出しました。他にもYahoo!が2019年にロゴを紫のサンセリフ体にして現代的な印象に変えたり、マイクロソフトがシンボルマークと統一感のあるシンプルな文字ロゴにしたりと、大小様々な企業が同様の動きを見せています。

・バーガーキングのロゴ / Roland Magnusson – stock.adobe.com
逆に、あえてセリフ体や装飾的なロゴを採用する例も少しずつ復活しています。先述のチョバーニやMediumのほか、米バーガーチェーン大手のBurger Kingは2021年にロゴを1970年代風のレトロな書体に戻し、大胆な懐古路線で話題を呼びました。このようにブランドごとの方向転換も起きており、ロゴデザインの世界は今まさに過渡期にあると言えるかもしれません。
専門家が語る今後のロゴデザインの可能性

それでは、今後のロゴデザインはどのような方向に進んでいくのでしょうか?専門家たちの見解や予測をいくつかご紹介します。
まず、多くのデザイン専門家が一致して指摘するのは「トレンドは常に変化し循環する」ということです。現在はサンセリフ体全盛とはいえ、これが一過性のブームで終わるのか、それとも定着するのかについては様々な意見があります。
肯定的な見方としては、「サンセリフ体ロゴへの移行はデジタル社会に対応した合理的な進化であり、当面はこのシンプル路線が主流を占め続けるだろう」というものがあります。実際、ここ10年ほど続いてきたミニマルデザイン志向はすぐには消えておらず、Webやアプリの世界では洗練されたサンセリフ体が引き続き標準となっています。サンセリフ体は可読性や汎用性という点で理にかなっており、「流行」というより「現代の標準」に近い存在になりつつあるとも言えるでしょう。

しかし一方で、新たな変化の兆しも見逃せません。懐古的な要素やユニークさの追求が再び注目され、セリフ体や装飾的なフォントの洗練された再解釈が増えてきているのです。例えば2024~2025年のタイポグラフィ動向として「クラシックなセリフ体の劇的カムバック」が挙げられています。ただしそれは単に昔の書体に戻るのではなく、「伝統と革新のバランスを取った新しいセリフ体」が主役になるとも言われます。
具体的には、伝統的なセリフ書体に現代的なアレンジを加えたり(太さの強弱を大胆にしたり、予想外の角度のセリフを付けたり)、クラシックな雰囲気を保ちつつモダンさも感じさせるフォントが台頭してくる予想です。デザイナーたちは「懐かしさ」だけでなく「新しさ」も備えた表現を模索しており、単純にサンセリフかセリフかの二者択一ではない、ハイブリッドなデザインが増えていくかもしれません。
また、タイポグラフィ技術の進歩も未来のロゴデザインに影響を与えるでしょう。可変フォント技術(バリアブルフォント – Variable Fonts)により、一つの書体で太さやセリフの有無を自在に変化させることも可能になってきています。将来的には、ロゴが状況に応じて動的に形を変えるといった演出も考えられます。例えば画面が小さい時はセリフを省き、大きなポスターではセリフを付けて伝統的な雰囲気を出す…そんな柔軟なロゴも夢ではありません。こうした新技術の普及も相まって、「ブランドの本質」を損なわずに様々な表情を見せられるロゴデザインが追求されていくでしょう。
専門家の中には、「結局のところ優れたブランディングは流行に流されすぎず、そのブランドらしさを軸に置いた上でトレンド要素を適度に取り入れることが重要だ」と指摘する声もあります。つまり、サンセリフ体にするかセリフ体にするかはあくまで手段であり、大切なのはブランドの個性やメッセージと書体の調和だということです。今後はその調和点を探るために、これまでの流行への反省を踏まえつつ、新旧様々なスタイルを柔軟に取り込む時代になるのではないでしょうか。
おわりに – ブームを超えて進化するロゴデザイン

企業ロゴのサンセリフ体化の潮流について、背景や歴史、心理効果、具体例、そして未来展望を見てきました。総括すると、この現象は単なる一過性のブームではなく、デジタル時代や文化の変化に適応したデザインの進化であると言えます。サンセリフ体ロゴの普及には合理的な理由があり、その影響は現在も強く続いています。
しかし同時に、デザインの世界では常に新たな創意工夫と差別化の模索が行われています。あるスタイルが主流になればなるほど、そこから逸脱した新しい表現が新鮮に映るものです。サンセリフ体一色になりがちな状況への反動として、セリフ体やより装飾的な要素を再評価する動きが出てきているのも自然な流れでしょう。
要するに、ロゴデザインは今後も揺れ動きながら発展していくということです。サンセリフ体化はその一つの章であり、今後どのように物語が展開していくかは、消費者の価値観や技術環境の変化、そしてデザイナーたちのクリエイティブな挑戦にかかっています。もしかすると数年後には「セリフ体のロゴが再び街にあふれている」なんてこともあるかもしれませんし、逆にさらにミニマルを極めた表現や全く新しい書体カテゴリーが登場しているかもしれません。
いずれにせよ、ブランドのロゴは時代とともに生きる生き物です。サンセリフ体への変化も一つの進化形態と捉え、ブームかどうかにとどまらず「なぜその選択がなされたのか」「それにより何を伝えようとしているのか」を考えてみると、企業やブランドが歩んでいるストーリーが見えてきて興味深いですね。これからロゴがどのように姿を変えていくのか、引き続き注目していきたいところです。
【参考資料】
Web Designer Depot: Why Big Brands Are Ditching Serif Fonts in Their Logos (https://webdesignerdepot.com/why-big-brands-are-ditching-serif-fonts-in-their-logos/)
Creative Review: The return of the serif (https://www.creativereview.co.uk/return-serif-type-trend/)
Monotype: What’s behind the rise of ‘quirky’ serifs?(Juan Villanueva氏・Carl Crossgrove氏の見解)(https://www.monotype.com/resources/articles/what-s-behind-the-rise-of-quirky-serifs)
Highsnobiety: Has Burberry Started an Anti-Sans-Serif Logo Trend? (https://www.highsnobiety.com/p/burberry-new-logo-trend/)
Marketing Week: Burberry ‘refocusing’ on brand to fuel turnaround (https://www.marketingweek.com/burberry-refocus-brand)
It’s Nice That: BMW unveils new flat and transparent logo, geared towards openness and digitisation (https://www.itsnicethat.com/news/bmw-new-logo-graphic-design-050320)
Design Work Life: 40 Typography Trends in 2025 (https://designworklife.com/typography-trends)
デザイン費用やプランを見たい
ASOBOADの具体的なデザイン制作料金については【ロゴの制作依頼】ページ からご覧いただけます。作例を見てから検討したい
これまでのASOBOADの制作事例やサンプルについては【ロゴの制作事例】ページ からご覧いただけます。まずは無料お見積もりから
ロゴなどのブランディングツールから、チラシやパンフレットといった販促物まで。あらゆる広告・グラフィックデザイン制作を、日本全国どこからでもオンラインで承ります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧