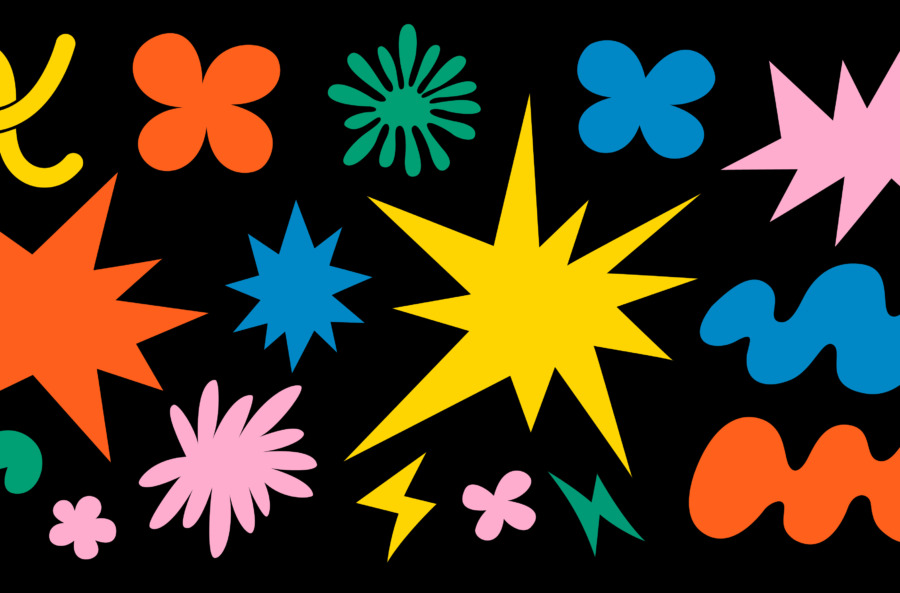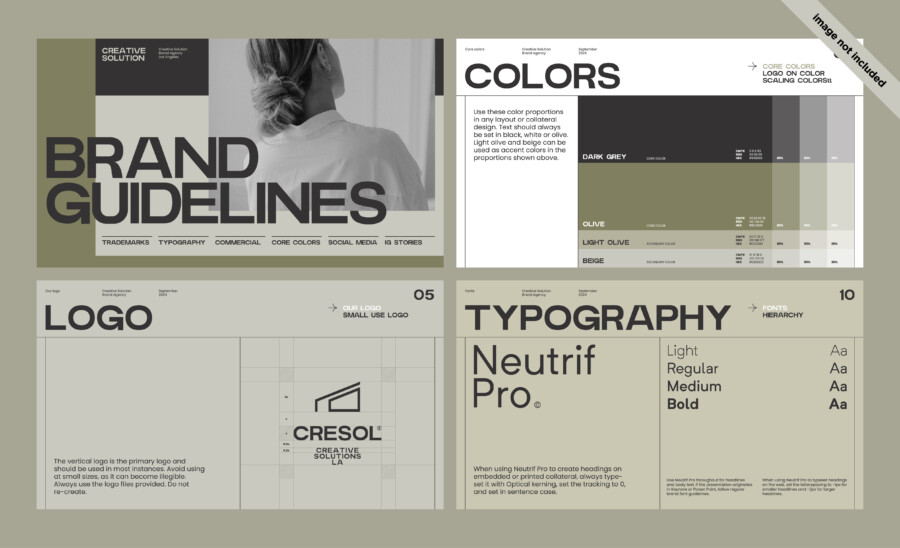街を歩いていたり、ウェブサイトを見ていたりするとき、ふと目にしたロゴの色から「あ、あの会社だ!」と思い出すこと、ありませんか? 赤い丸に白い文字、青い鳥のシルエット、緑の人魚…。色が持つ力って、本当にすごいですよね。
実は、ロゴの色は単なるデザイン要素ではありません。色は、ブランドの個性やメッセージを伝え、顧客との感情的なつながりを築くための強力なコミュニケーションツールなんです。
この記事では、そんな「色」が持つパワーを最大限に引き出し、あなたのブランドイメージを効果的に伝えるためのロゴ配色戦略について、一緒に考えていきたいと思います。「なんとなく好きな色だから」という理由だけで色を選んでしまう前に、ぜひこの記事を読んで、戦略的な色選びのヒントを見つけてくださいね!
なぜロゴの色はそんなに重要なのか?色の持つ心理的効果

「たかが色でしょ?」と思われるかもしれませんが、色は私たちが思う以上に、人の感情や行動に影響を与えています。これを色彩心理学と呼んだりしますが、難しく考える必要はありません。普段の生活を思い返してみてください。
赤色を見ると、情熱、エネルギー、興奮、注意などを感じませんか?セール告知や信号機など、注目を集めたい場所によく使われていますよね。
青色はどうでしょう?空や海を連想させるからか、信頼感、誠実さ、冷静さ、落ち着きといった印象を与えます。多くの企業、特に金融機関やIT企業が好んで使う色です。
緑色は、自然、健康、成長、安らぎなどをイメージさせます。環境に配慮したブランドや、オーガニック製品、リラクゼーション関連のサービスなどでよく見かけますね。
黄色は、明るさ、楽しさ、幸福感、注意喚起といった印象です。子ども向けの製品や、手頃感を出したいサービスなどに使われることがあります。
オレンジ色は、親しみやすさ、活気、創造性などを感じさせます。赤色ほど強すぎず、黄色ほど軽すぎない、バランスの取れたエネルギッシュな色です。
紫色は、高貴さ、神秘性、創造性、洗練といったイメージがあります。高級ブランドや、スピリチュアルな分野、クリエイティブな業界で使われることがあります。
黒色は、力強さ、高級感、権威、洗練などを表現します。ファッションブランドや、重厚感を出したい製品によく使われます。
白色は、清潔感、純粋さ、シンプルさ、平和などを象徴します。ミニマリストなデザインや、医療・ヘルスケア分野で好まれます。
灰色は、中立性、落ち着き、洗練、知性などを感じさせます。他の色を引き立てる役割も果たし、モダンで落ち着いた印象を与えたい場合に有効です。
もちろん、これらの印象は文化や個人の経験によって異なりますし、色の組み合わせやトーン(明るさ、鮮やかさ)によっても大きく変わってきます。しかし、一般的に特定の色が特定の感情やイメージを呼び起こしやすい、ということは覚えておいて損はありません。
ロゴの色は、顧客があなたのブランドに初めて触れる際の「第一印象」を大きく左右します。言葉よりも早く、直感的にブランドの個性を伝えることができるのが、色の持つ大きな力なのです。
ブランドイメージと色を結びつける – どんな印象を与えたい?

さて、色が持つ心理的な効果がわかったところで、次はそれをどうブランドイメージに結びつけていくかを考えてみましょう。大切なのは、「あなたのブランドが、顧客にどんな印象を持ってもらいたいか?」を明確にすることです。
ブランドのコアバリュー(核となる価値観)を定義する
- あなたのブランドが最も大切にしていることは何ですか? (例: 信頼性、革新性、親しみやすさ、環境への配慮、楽しさ、高級感)
- どんな個性を持ったブランドだと思われたいですか? (例: 若々しい、落ち着いている、エネルギッシュ、洗練されている、伝統的)
ターゲット顧客を明確にする
- どんな人に製品やサービスを届けたいですか? (年齢、性別、ライフスタイル、価値観など)
- ターゲット顧客は、どんな色に好感を持つ傾向があるでしょうか?
競合他社のロゴカラーを調査する
- 同じ業界の競合他社は、どんな色を使っていますか?
- 彼らが伝えようとしているブランドイメージは何でしょうか?
他社と差別化するために、あえて違う色を選ぶべきか、それとも業界の慣習に合わせた方が良いか、戦略的に考えましょう。
これらの要素を整理することで、あなたのブランドにふさわしい色の方向性が見えてくるはずです。
例えば…
- 信頼性と誠実さを重視する法律事務所やコンサルティング会社なら、青色や灰色を基調とすることで、落ち着きとプロフェッショナルな印象を与えられます。
- 子ども向けの楽しいおもちゃブランドなら、黄色やオレンジ色、あるいは複数の明るい色を組み合わせることで、楽しさやワクワク感を表現できるでしょう。
- 自然派化粧品ブランドなら、緑色やアースカラー(茶色、ベージュなど)を使うことで、自然由来であることや優しさを伝えられます。
- 最先端のテクノロジー企業であれば、未来感や洗練されたイメージを出すために、青色や黒、シルバーなどを効果的に使うかもしれません。あるいは、革新性を強調するために、鮮やかな差し色を加えることも考えられます。
このように、「伝えたいブランドイメージ」と「色が持つ心理的効果」を結びつけることが、戦略的なロゴ配色への第一歩となります。
実践!ロゴ配色戦略のステップ

ブランドイメージに合った色の方向性が見えてきたら、いよいよ具体的な配色を決めていきます。ロゴの色は一つだけとは限りません。多くの場合、主要な色(プライマリーカラー)、補助的な色(セカンダリーカラー)、そして強調色(アクセントカラー)を組み合わせて構成されます。
プライマリーカラーを決める
ブランドの最も核となるイメージを表現する色を選びます。これがロゴの大部分を占める、あるいは最も印象に残る色になります。前述のブランドイメージと色の関連性を参考に、最もふさわしい色を選びましょう。
セカンダリーカラーを選ぶ
プライマリーカラーを補完し、デザインに深みやバリエーションを与える色です。プライマリーカラーと調和しつつ、ブランドの別の側面(例えば、信頼性の中にも親しみやすさを加えたい、など)を表現できる色を選びます。
類似色(色相環で隣り合う色)を選ぶとまとまりのある印象に、補色(色相環で反対側にある色)を選ぶとコントラストが生まれ、ダイナミックな印象になります。
アクセントカラーを加える(任意)
ロゴの中で特に注目させたい部分や、少しだけ遊び心を加えたい場合に使われる、少量の色です。ウェブサイトのボタンや、重要な情報を示すアイコンなど、ロゴ以外のデザイン要素でも活用できます。
全体のバランスを崩さないよう、慎重に選びましょう。鮮やかな色を選ぶことが多いですが、全体のトーンに合わせることも重要です。
色のトーン(明度・彩度)を調整する
同じ「青」でも、明るく鮮やかな青と、深く落ち着いた紺色では、与える印象が全く異なります。ブランドイメージに合わせて、色の明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)を微調整しましょう。
- 明るい色:ポジティブ、軽やか、若々しい
- 暗い色:重厚感、高級感、落ち着き
- 鮮やかな色: エネルギッシュ、活発、目立つ
- くすんだ色:穏やか、洗練、大人っぽい
組み合わせのバランスと可読性を確認する
選んだ色の組み合わせが、視覚的に心地よいか、バランスが取れているかを確認します。色の使いすぎは、ごちゃごちゃした印象を与えかねません。一般的には3色程度に抑えるのが良いとされています。
特にロゴに文字が含まれる場合は、背景色と文字色のコントラストが十分で、可読性が確保されているかを必ずチェックしましょう。小さく表示されたときや、白黒で印刷されたときでも、きちんと認識できることが重要です。
様々な媒体での見え方を考慮する
ロゴはウェブサイト、名刺、パンフレット、商品パッケージ、看板など、様々な場所で使われます。
デジタル(RGB)と印刷(CMYK)では色の再現性が異なるため、どちらの媒体でも意図した色味が出せるように、カラーコード(HEX, RGB, CMYK)をしっかりと管理しましょう。
異なる背景色の上にロゴを配置するケースも想定し、汎用性の高い配色を心がけましょう。
よくある配色パターンとその印象
配色に迷ったら、一般的な配色パターンを参考にしてみるのも良いでしょう。
モノクロマティック配色(単色構成)

一つの色相の明度や彩度を変えた色の組み合わせ。(例:濃い青、普通の青、水色)
まとまりがあり、洗練された、落ち着いた印象を与えます。シンプルで上品なブランドイメージに適しています。
アナロガス配色(類似色構成)

色相環で隣り合う色(例:黄色、黄緑、緑)を使った組み合わせ。
調和が取れており、穏やかで自然な印象を与えます。安心感や親しみやすさを出したい場合に有効です。
コンプリメンタリー配色(補色構成)

色相環で正反対に位置する色(例:赤と緑、青とオレンジ)の組み合わせ。
強いコントラストが生まれ、ダイナミックでエネルギッシュな印象を与えます。目立たせたい、活気を出したい場合に効果的です。ただし、使い方によっては目がチカチカすることもあるので、面積比などに注意が必要です。
トライアド配色(3色構成)

色相環で等間隔に位置する3色(例:赤、黄、青)の組み合わせ。
バランスが取れつつも、カラフルで活気のある印象を与えます。創造性や多様性を表現したい場合に適しています。
これらのパターンはあくまで基本ですが、色選びの出発点として役立つはずです。
ロゴ配色で避けたい注意点

戦略的に色を選んだつもりでも、思わぬ落とし穴があることも。以下の点に注意しましょう。
色数が多すぎる:色を使いすぎると、まとまりがなくなり、ブランドメッセージがぼやけてしまいます。シンプル・イズ・ベストを心がけ、多くても3〜4色程度に抑えるのが無難です。
トレンドだけを追いかける:その時々の流行色を取り入れるのも一つの手ですが、トレンドは移り変わるものです。ブランドの核となるイメージからかけ離れた色を選んでしまうと、後々ちぐはぐな印象を与えかねません。長く愛されるブランドを目指すなら、普遍的な価値観に基づいた色選びが重要です。
文化的な意味合いを無視する:色が持つ意味は、国や文化によって異なる場合があります。例えば、日本ではお祝い事に使われる赤色が、西洋では危険信号の意味合いを持つことも。グローバル展開を視野に入れている場合は、ターゲットとする地域の文化における色の意味合いをリサーチすることが不可欠です。
可読性・視認性の欠如:デザイン性を重視するあまり、文字が読みにくかったり、ロゴの形が認識しづらかったりするのは本末転倒です。特に背景色とのコントラストには十分注意しましょう。
競合との類似性が高すぎる:差別化を図るつもりが、競合他社と似たような色を選んでしまうと、顧客に混同される可能性があります。意図しない限り、独自性を出せる配色を意識しましょう。
ロゴだけじゃない!ブランドカラーの一貫性

ロゴの色が決まったら、それで終わりではありません。その色は、あなたのブランド全体を象徴する「ブランドカラー」として、あらゆるコミュニケーションツールで一貫して使用していくことが重要です。
- ウェブサイト:ヘッダー、フッター、ボタン、リンク色など
- マーケティング資料:パンフレット、広告、プレゼンテーション資料など
- SNS:プロフィール画像、カバー画像、投稿テンプレートなど
- 商品パッケージ:製品自体の色、包装デザインなど
- 店舗デザイン:内装、看板、スタッフのユニフォームなど
あらゆる顧客接点でブランドカラーを一貫して使用することで、ブランドの認知度が高まり、顧客の中に統一されたブランドイメージが強く記憶されるようになります。「この色といえば、あのブランドだよね!」と思ってもらえる状態を目指しましょう。
まとめ – 色は雄弁なブランドの代弁者

ロゴの配色は、単なる見た目の問題ではなく、ブランドの価値観や個性を伝え、顧客との関係を築くための重要な戦略です。
- 色が持つ心理的効果を理解する
- 自社のブランドイメージとターゲット顧客を明確にする
- 競合を分析し、差別化を図る
- プライマリー、セカンダリー、アクセントカラーをバランス良く組み合わせる
- 可読性や汎用性を考慮する
- ブランド全体で色の一貫性を保つ
これらのステップを踏むことで、あなたのブランドは色という強力な武器を手に入れ、顧客の心に響くメッセージを効果的に届けることができるはずです。
「なんとなく」で色を選ぶのではなく、一つ一つの色に意味を持たせ、戦略的に活用していく。それが、ブランドイメージを最大化するための第一歩です。ぜひ、あなたのブランドに最適な「色」を見つける旅を楽しんでくださいね!
デザイン費用やプランを見たい
ASOBOADの具体的なデザイン制作料金については【ロゴの制作依頼】ページ からご覧いただけます。作例を見てから検討したい
これまでのASOBOADの制作事例やサンプルについては【ロゴデザイン事例】ページ からご覧いただけます。まずは無料お見積もりから
ロゴなどのブランディングツールから、チラシやパンフレットといった販促物まで。あらゆる広告・グラフィックデザイン制作を、日本全国どこからでもオンラインで承ります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧