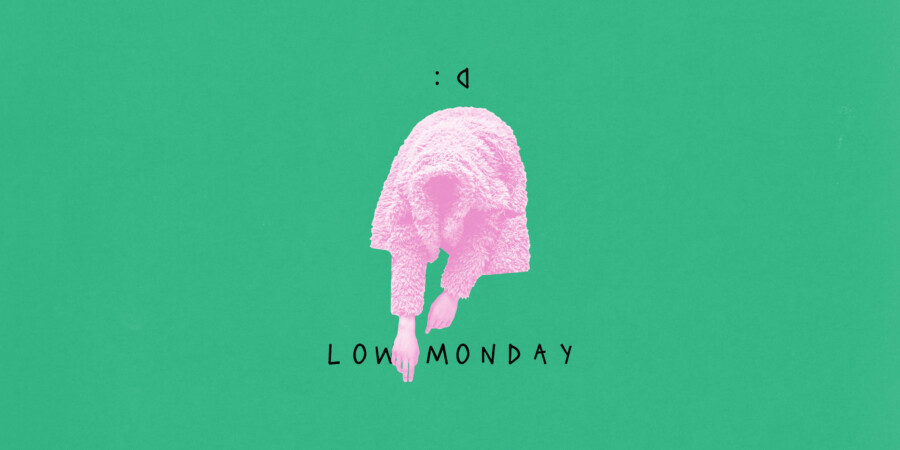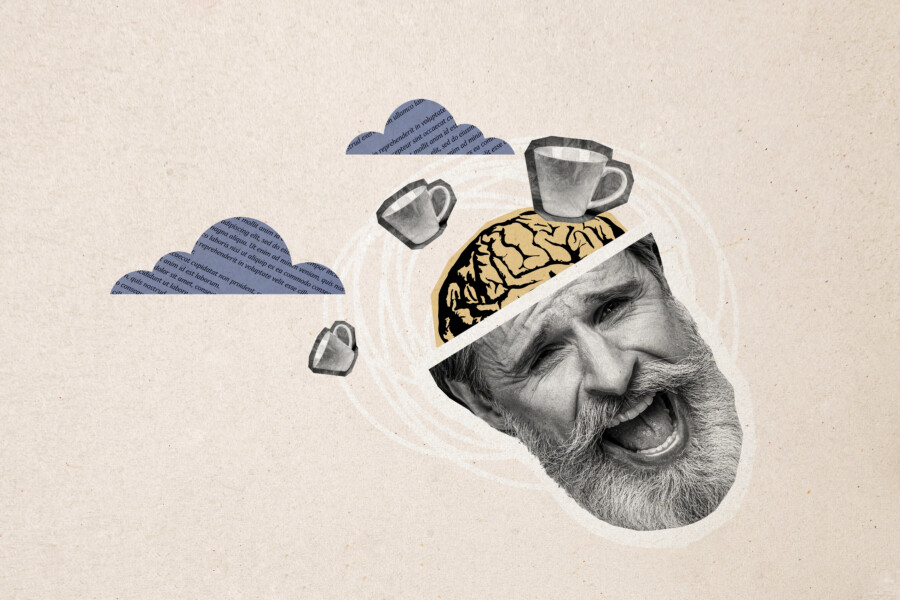失敗を共有する為に毒キノコを試食する必要はない
僕たちは誰しも、一度や二度は「やってしまった」と頭を抱えるような失敗を経験していると思います。もちろん、失敗から学ぶことは大きいですし、実際に痛い目を見なければわからないことも多いでしょう。
ただ、だからといって部下や後輩に同じ“毒キノコ”を食べさせてまで失敗を体験させる必要があるのかと言われると、少し違和感を覚えます。そこで今回は、なぜ失敗を共有することが大切なのか、そして失敗をどう伝えれば相手にプラスの影響を与えられるのかを考えてみます。
失敗を共有する理由

学びの効率を上げる
自分が体験した失敗談を周囲に共有することは、「恥をさらす」行為ではありません。「みんなで同じ失敗を繰り返さないための効率的な情報共有」です。もし毒キノコを食べてしまうような痛い失敗をした場合、その本人は二度と同じことを繰り返さないでしょう。しかし、その経験談を周囲と共有しなければ、部下や後輩も同じ失敗を繰り返す可能性が残ります。誰かがすでに通った“地雷原”を教えてもらえるなら、わざわざ踏まなくても済むはずです。
チームの結束力を高める
失敗を包み隠さずオープンにする文化は、チームの雰囲気を前向きにしてくれます。みんなが失敗を共有し合うことで、「自分だけじゃないんだ」と安心できる気持ちが生まれやすくなります。「大丈夫、こうすれば次はうまくいくかもしれないよ」とアドバイスし合うことで、失敗に対する恐怖やプレッシャーが軽減されることも多いです。互いの弱さや苦労を知ると、不思議なことにお互いをサポートし合おうとする空気が育まれます。
新たなアイデアのヒントになる
意外かもしれませんが、失敗談を共有すると、そこから新たなアイデアが生まれることも少なくありません。例えば、毒キノコを食べてしまった人が、「どうしたら毒を見分けられたのか」「他に安全な食べ方はなかったのか」を振り返ることがきっかけで、新しい研究や工夫が進むかもしれません。仕事での失敗も同じです。ミスやエラーの要因をみんなで検討する過程で、今まで気づかなかった改善点や次なるチャレンジの糸口が見えてくるはずです。
失敗の伝え方を工夫しよう
大切なのは共感と具体性
失敗を共有するときは、失敗の背景や状況を具体的に伝えることが重要です。ただ「失敗しました」と言うだけでは情報量が少なく、周囲はイメージしづらいかもしれません。「何が、どのように、どうしてそうなったのか」「原因はどこにあったのか」「取り返すためにどんな行動をしたのか」をできる範囲で共有すると、周囲が自分ごととして考えやすくなります。
また、語り口調を一方的にするより、「実はかなり焦ったんだよね」「周囲にすごく迷惑をかけてしまって申し訳なかった」というように率直な感情を添えると、聞き手も共感しやすくなります。
教訓や次のアクションを明確に
失敗談に添える形で、「じゃあ次はどうすればいいのか」を一緒に考える工夫も大切です。単に「こんなひどい失敗をした」という話だけでは、聞いている側も対応策がわからずに困ることが多いです。そこで、失敗の教訓や改善策をセットで示すと、学びを次のステップに活かす道筋がクリアになります。
「事前に確認リストを作っておくべきだった」「この工程は自分だけでなくチーム全体で管理したほうがミスが減りそう」など、次のアクションが具体化されていると、周囲は自然に同じ失敗を繰り返さないための準備ができるようになります。
無理に苦い経験をさせない

強要はモチベーションを削ぐ
「失敗こそ成長の糧だから」という考え方は理解できますが、それを強要するのは相手のモチベーションを下げかねません。上司が「自分も昔は失敗したから、お前も同じ失敗を味わっておけ」というスタンスで接すれば、当然ながら反発や萎縮を生みやすいです。
本来、先輩や上司は「苦い経験を二度と繰り返さないためにはどうすればいいか」を考えて行動するべき立場です。むしろ、「自分はこういう辛い失敗をしたから、あなたには回避してほしい」と率直に伝え、サポートしてあげるのが理想です。
安全な範囲で経験する機会を用意する
毒キノコ級の大惨事を無理に味わわせる必要はありませんが、まったく失敗のリスクがない環境だと、挑戦も生まれにくくなります。そこで、安全策を講じたうえで多少のリスクがあるプロジェクトや小さなトライアルを部下や後輩に任せるのは有効です。失敗しても大怪我をせずに済むように、フォロー体制を整えておくと安心感が高まります。こうした“安全な失敗”の機会が用意されている組織では、メンバーが自発的に行動しやすくなるはずです。
失敗から組織に学びをもたらすために

失敗を許容する雰囲気作り
組織が失敗から学ぶためには、失敗が責められたり隠されたりしない風土が必要です。リーダー自身が率先して失敗談を共有し、「失敗してもリカバリーができるし、その経験は次に活かせる」というメッセージを発信することで、チームメンバーも自分のミスをオープンにしやすくなります。
ここで大切なのは、失敗の責任をリーダー自身がどう捉えているかです。「誰が悪いのか」ではなく、「どうすれば全員で改善できるか」を常に意識する姿勢が求められます。
失敗を分析して次に活かす仕組み
「どうして失敗が起きたのか」を振り返るために、チームで定期的に振り返りミーティングを行うのも有効です。各メンバーの報告をただ聞くだけではなく、次に活かすための具体的な行動プランをまとめるまでがセットと考えると、時間を有意義に使えます。ポイントは、「原因追及」ではなく「未来の成功のための対策づくり」をメインにすること。そうすることで、失敗をポジティブな学びに変換しやすくなります。
まとめ
失敗を恐れずに共有することで、同じミスを繰り返さない学びや、チームの結束力が高まる効果が期待できます。だからといって、毒キノコをわざわざ部下や後輩に食べさせる必要はありません。僕たちが先に味わった苦い経験や教訓は、自分だけに留めるのではなく、周囲にシェアすることで初めて組織全体の力となります。
適切な形で失敗を伝え、互いの挑戦をサポートし合う文化を作れば、安心してチャレンジできる環境が整いやすくなるでしょう。毒キノコを回避しつつ、次の成功につなげるために、失敗談を上手にシェアしていきたいものです。
失敗から学ぶことは確かにあります。毒キノコを食べて悶絶したら、二度と食べないでしょう。だからと言って、部下に同じ毒キノコを食べさせる必要は無いと思う。 それ危ないから気をつけてね。と教えてあげれば良いだけ。
X (Twitter) – Jul 24, 2020
私個人への依頼について
私個人(トミナガハルキ)への依頼についてはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。広告デザイン制作、PR、執筆(書籍・記事)、SEOやサイト運営に関するアドバイス等を行なっています。リーズナブルにデザインを依頼したい
デザイン事務所AMIXの運営する【デザイン作成のASOBOAD】ではチラシ制作等をはじめ、各種広告デザインをリーズナブルな料金で行なっています。(※こちらは、主にスタッフがデザイン作成を行なっています。)