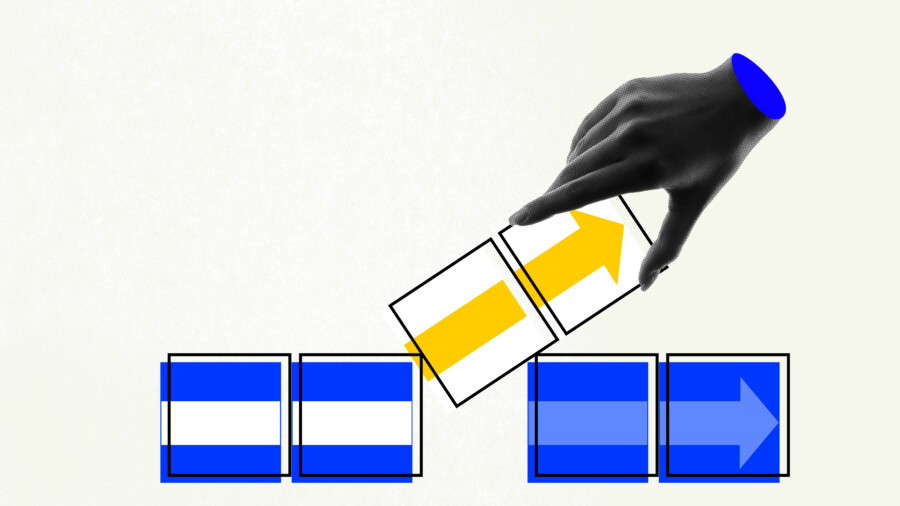挑戦者を悩ます「どうせ失敗する」の声 〜 その正体と付き合い方
何か新しいことに挑戦するとき、ワクワクする気持ちと同じくらい、もしかしたらそれ以上に「うまくいかなかったらどうしよう」という不安が頭をよぎること、ありますよね。僕もデザインの仕事をしていると、新しい表現や技術に挑戦する場面がありますが、いつも上手くいくわけではありません。むしろ、試行錯誤の末に「これは違うな」とボツになるアイデアの方が多いかもしれません。
新しい挑戦において、成功と失敗のどちらが起こりやすいかといえば、統計的に見ても失敗の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。何かを生み出したり、変えたりしようとする際には、避けて通れない現実だと思います。
なぜ挑戦には「失敗」がつきものなのか

考えてみれば当たり前かもしれませんが、新しいことへの挑戦は、まだ誰も知らない、あるいは自分が経験したことのない領域へ足を踏み出す行為です。そこには、確立された「正解」のルートがあるわけではありません。
デザインのプロセスを考えてみても、最初のアイデアがそのまま最終形になることは稀です。いくつものラフスケッチを描き、モックアップを作り、試してみては修正し、時には根本から考え直す。この繰り返しの中で、ほとんどの試みは「失敗」あるいは「最終案ではないもの」として、次のステップへの糧となっていきます。
これはデザインに限らず、新しいビジネス、研究開発、芸術活動、あるいは個人的なスキルアップなど、あらゆる挑戦に共通していえることだと思います。未知の要素が多ければ多いほど、試行錯誤の回数は増え、結果的に「失敗」とカウントされる経験が多くなるのは、ある意味、自然の摂理なのかもしれません。
「ほら、言った通りだろ?」の正体

挑戦には失敗がつきもの。この事実は、時として厄介な状況を生み出します。周りを見渡すと、何か新しい動きがあるたびに、否定的な意見を口にする人が一定数いることに気づくでしょう。
彼らは、挑戦がうまくいかなかった時に「ほら、言った通りだろ?」「だからやめておけと言ったのに」と、まるで自分の予測が正しかったかのように振る舞うことがあります。でも、少し立ち止まって考えてみると、彼らは本当に「未来を予測する能力」が高いのでしょうか?
僕は、そうではないと思っています。
彼らは、挑戦における成功と失敗の確率を、肌感覚で理解しているだけなのかもしれません。つまり、挑戦が失敗する確率の方が高いことを知っていて、常に「失敗する」という方に賭けている。確率的に考えれば、彼らの”予想”は当たりやすいわけです。
ポーカーで、常に一番弱い役に賭け続けるようなもの、と言ったら言い過ぎでしょうか。もちろん、たまには強い役が出ることもありますが、確率的には弱い役の方が圧倒的に出やすい。だから、「弱い役が出る」と予想し続ければ、当たる回数は多くなります。
でも、それは決して「読みが鋭い」わけではありませんよね。ただ、最も起こりやすい出来事を指摘しているに過ぎません。
問題なのは、この「当たりやすい予想」を繰り返すことで、「自分は常に正しい」「物事の本質を見抜いている」と、ある種の万能感を抱いてしまうケースがあることです。そうなると、他者の挑戦を応援するどころか、足を引っ張るような言動につながってしまうこともあり、少し困ったものだなと感じます。
否定的な声とどう向き合うか

では、僕たち挑戦する側は、こうした否定的な声とどう向き合っていけばいいのでしょうか。
まず大切なのは、「失敗確率が高いのは当たり前」と腹を括ることかもしれません。失敗を過度に恐れたり、否定的な意見に心が揺さぶられたりするのは、どこかで「挑戦は成功して当然だ」という思い込みがあるからかもしれません。失敗はプロセスの一部であり、データ収集の機会なのだと捉えることで、少し心が軽くなるはずです。
次に、すべての否定的な意見を鵜呑みにしないこと。もちろん、中には建設的な批判や、自分では気づかなかった視点を提供してくれる貴重なフィードバックもあります。そうした声には真摯に耳を傾けるべきです。
しかし、単に確率の高い「失敗」を指摘しているだけの声や、挑戦そのものを揶揄するような声に、心をすり減らす必要はありません。その声が、具体的な問題点の指摘や改善案を伴っているか、それとも単なる感情的な否定なのかを見極めることが大切です。
僕自身、デザイン案に対して厳しいフィードバックをいただくこともありますが、それが具体的な理由や代替案に基づいている場合は、たとえ耳が痛くても、改善のための重要なヒントとして受け止めるようにしています。一方で、理由なき否定や漠然とした不安を煽るだけの意見は、参考程度に留めるように意識しています。
それでも挑戦し続ける価値
失敗する確率の方が高い。周りからは否定的な声も聞こえてくる。それでも、なぜ僕たちは挑戦を続けるのでしょうか。
それは、挑戦の先にある「成長」や「発見」、そして稀に訪れる「成功体験」が、計り知れない価値を持っているからだと思います。
失敗は、確かに痛みを伴います。時間や労力が無駄になったように感じることもあるでしょう。でも、その経験から「なぜうまくいかなかったのか」「どうすれば改善できるのか」を学ぶことができます。この学びこそが、自分自身を成長させ、次のステップへ進むための推進力となります。たくさんの「失敗」という名のデータが集まるからこそ、成功への解像度が上がっていくのではないでしょうか。
そして、多くの失敗の先にたどり着いた成功体験は、格別な喜びと達成感をもたらしてくれます。それは、単に「うまくいった」という結果だけでなく、困難を乗り越えたプロセス全体が、自信や次なる挑戦への意欲に繋がるからです。
何より、挑戦をやめてしまったら、新しいものは何も生まれません。現状維持は、後退と同じとも言われます。たとえ失敗確率が高くても、未来をより良くするために、あるいは自分自身の可能性を広げるために、僕たちは挑戦し続ける必要があるのではないでしょうか。
失敗は、挑戦者の勲章
挑戦において、失敗は避けて通れない現実です。成功よりもずっと頻繁に起こる出来事といえます。そして、その「失敗確率の高さ」を利用して、否定的な意見を繰り返す人もいます。
でも、それに惑わされる必要はないと思います。大切なのは、失敗を恐れすぎず、それを学びの機会と捉えること。そして、心無い否定と建設的な批判を見極め、挑戦を続ける勇気を持つことです。
一つ一つの失敗は、あなたが前に進もうとしている証であり、挑戦者の勲章のようなもの。たくさんの試行錯誤の中からこそ、本当に価値のあるものが生まれるのだと、僕は信じています。
挑戦することにおいて、成功と失敗の確率は明らかに失敗の方が高いわけです。何でも否定する人は”予想”が当たっているんじゃなくて、高確率で発生する失敗に賭けてるんだからそりゃ当たりますよね。でもって、”そら見ろ、俺はいつも正しい”と増長していくから、困ってしまいます。
X (Twitter) – Aug 26, 2018
私個人への依頼について
私個人(トミナガハルキ)への依頼についてはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。広告デザイン制作、PR、執筆(書籍・記事)、SEOやサイト運営に関するアドバイス等を行なっています。リーズナブルにデザインを依頼したい
デザイン事務所AMIXの運営する【デザイン作成のASOBOAD】では動画制作等をはじめ、各種広告デザインをリーズナブルな料金で行なっています。(※こちらは、主にスタッフがデザイン作成を行なっています。)