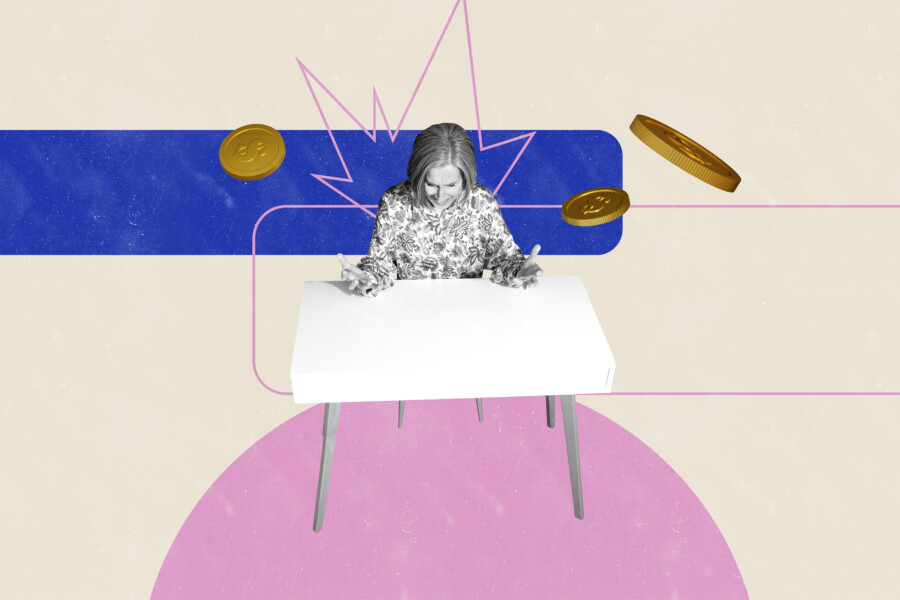「自分の物差し」で他人を測らない ~戦士と村人に学ぶ価値観の多様性~
世の中には、様々な働き方や生き方がありますよね。リスクを恐れず新しい道を切り拓こうとする人がいる一方で、安定した環境で着実に自分の役割を果たしたいと考える人もいます。
僕は時々、前者を「荒野を行く戦士」、後者を「村で暮らす人々」に喩えて考えることがあります。どちらが良い・悪いという話ではありません。ただ、それぞれが大切にするもの、目指す場所が違うのだと思うのです。
今回は、この「戦士」と「村人」という比喩を手がかりに、多様な働き方や価値観、そして互いを尊重することの大切さについて、考えてみたいと思います。
「戦士」とは誰か? – 荒野をゆく挑戦者たち
僕が「戦士」と表現するのは、主にフリーランスや起業家といった、いわば自ら道を切り拓いていく人たちのことです。彼らは、安定した組織の後ろ盾がない「荒野」で、自分のスキルやアイデア、そして覚悟を武器に戦っています。
- 常に挑戦し続ける姿勢:新しい仕事の獲得、事業の拡大、未知の分野への挑戦など、現状維持ではなく、常に前進しようとする強い意志を持っています。
- 高いリスクと隣り合わせ:収入の不安定さ、事業失敗のリスク、保証のない未来。そうした不確実性を引き受け、それでも進むことを選びます。
- 自己責任の世界:成功も失敗も、すべて自分の責任。誰かのせいにはできません。その厳しさが、彼らをさらに強くします。
- 仲間との絆:同じように荒野で戦う「戦士」同士は、互いの苦労や喜びを深く理解できます。だからこそ、励まし合い、時には厳しく発破をかけ合うことで、互いを高め合っていける。これは素晴らしい関係性だと思います。
彼らの生き様は、傍から見れば刺激的で、格好良く映ることも多いでしょう。実際に、彼らの挑戦が世の中に新しい価値を生み出したり、多くの人に勇気を与えたりすることも少なくありません。僕自身も、そうした方々の話を聞くと、奮い立つものを感じます。
「村人」でありたいという選択 – 安定と貢献の中で輝く
一方で、「村人」と表現したのは、組織に属したり、安定した環境の中で自分の役割を果たしたりすることを選ぶ人たちです。彼らは、必ずしも「戦士」のように自ら荒野を切り拓くことは望んでいません。
- 安定した基盤:予測可能な収入、福利厚生、確立された業務プロセス。こうした安定した環境は、日々の生活に安心感をもたらします。
- 組織への貢献:チームの一員として、あるいは特定の役割を担うことで、大きな目標達成に貢献します。個人の力だけでは成し得ないことを、組織の中で実現していくことに価値を見出します。
- 専門性の追求:安定した環境だからこそ、特定の分野のスキルや知識をじっくりと深め、専門家として活躍することも可能です。
- ワークライフバランス:「戦士」のように常に仕事のことを考えているのではなく、プライベートな時間や家族との時間を大切にしたい、と考える人も多いでしょう。
ここで強調したいのは、「村人」であることが「戦士」に劣っているわけでは全くない、ということです。むしろ、社会や組織は、こうした「村人」一人ひとりの確実な仕事によって支えられています。安定した「村」があるからこそ、「戦士」も安心して挑戦に出かけられるのかもしれません。
「ずっと村人がいい」という選択は、臆病なのでも、向上心がないのでもありません。それは、その人自身の価値観に基づいた、尊重されるべき立派な生き方の一つです。
なぜ「戦士の掟」の押し付けは問題なのか?

問題なのは、一部の「戦士」あるいは「戦士」に憧れる人が、その価値観(=戦士の掟)を「村人」であることを望む人にまで押し付けようとすることです。
例えば、こんな場面はありませんか?
- 安定志向の同僚に対して、「もっと挑戦しないの?」「リスクを取らないと成長しないよ」と、半ば強引に独立や起業を勧める。
- 定時で帰ろうとする人を見て、「意識が低い」「もっとコミットすべきだ」と内心で(あるいは口に出して)批判する。
- 「大きな夢を持て」「現状維持は後退だ」といったスローガンを、本人が望んでいないのに一方的に浴びせる。
これは、例えるなら、村で畑を耕し、家族との穏やかな暮らしを大切にしたいと思っている人に、「お前も剣を取って、ドラゴン退治に行くべきだ!」と無理強いするようなものです。本人は、畑を豊かにすることに誇りを持ち、村の平和を守ることに貢献したいのかもしれないのに。
このような価値観の押し付けは、相手を不快にさせるだけでなく、時には自己肯定感を奪い、精神的に追い詰めてしまう可能性すらあります。人はそれぞれ、異なる幸せの形、異なる成功の定義を持っています。それを無視して、一方的な物差しで測ろうとすることは、とても乱暴な行為だと僕は思います。
デザインの世界にもいる「戦士」と「村人」
これは、僕らがいるデザインの世界にも当てはまります。
フリーランスのデザイナーとして独立し、自ら仕事を取り、プロジェクトを率いていくのは「戦士」的な働き方かもしれません。常に新しいスキルを学び、人脈を広げ、変化に対応していく必要があります。刺激も多いですが、不安定さも伴います。
一方、企業や制作会社のインハウスデザイナーとして、チームで協力しながら特定のブランドやサービスのデザインに貢献するのは、「村人」的な働き方に近いかもしれません。安定した環境で専門性を深めたり、大きなプロジェクトに関わったりする機会があります。
どちらが良い・悪いではありません。どちらの働き方にも、それぞれ求められるスキル、やりがい、そして大変さがあります。大切なのは、自分がどちらのタイプに近く、どちらの環境でより自分の力を発揮し、幸福を感じられるかを知ることではないでしょうか。
僕自身も、キャリアの中で様々な働き方を経験してきました。その中で、自分はどちらかというと「戦士」的な気質も持ち合わせているけれど、安定した環境でじっくり制作に打ち込む「村人」的な時間も、同じくらい大切だと感じています。もしかしたら、多くの人は、完全な「戦士」でも「村人」でもなく、その間を揺れ動いたり、両方の要素を併せ持ったりしているのかもしれませんね。
互いを理解し、尊重し合うために
では、どうすれば私たちは、異なる価値観を持つ人たちと心地よく共存していけるのでしょうか。
- 自分の価値観を絶対視しない:まず、「自分の常識は、他人の非常識かもしれない」と心に留めておくことが大切です。「戦士」には「戦士」の理屈があり、「村人」には「村人」の理屈があります。どちらが絶対的に正しいということはありません。
- 相手の選択を尊重する:なぜ相手はその働き方、生き方を選んでいるのだろう?と想像力を働かせてみましょう。その背景には、その人なりの価値観や、大切にしたいものがあるはずです。それを頭ごなしに否定せず、まずは受け入れる姿勢が重要です。
- 安易なアドバイスをしない:特に、相手から求められてもいないのに、「もっとこうすべきだ」といったアドバイスをするのは控えたいものです。良かれと思って言ったことが、相手にとっては大きなお世話、あるいは価値観の押し付けになってしまう可能性があります。
- 多様性を力として認識する:社会や組織は、多様な人がいるからこそ豊かになります。「戦士」の突破力と、「村人」の安定感。その両方が組み合わさることで、より強く、しなやかな全体が生まれるのではないでしょうか。
違いを問題として捉えるのではなく、力として認識する視点が大切です。
まとめ – それぞれの場所で、自分らしく輝く
フリーランスや起業家といった「戦士」たちが互いを鼓舞し合うのは、素晴らしいことです。そのエネルギーが、社会を前進させる力になることもあります。
しかし、誰もが「戦士」になる必要はありません。「村人」として、安定した場所で、自分の役割を果たし、穏やかな幸せを追求することも、同じように尊い生き方です。
大切なのは、自分がどちらの生き方を望んでいるのかを見つめ、そして、自分とは違う生き方を選んでいる他者を尊重すること。
「戦士の掟」を振りかざすのではなく、それぞれの場所で、それぞれのやり方で輝こうとしている人を、温かい目で見守り、時にはそっと応援できる。そんな関係性が、これからの社会や、僕たちが働くデザイン業界にもっと増えていったら素敵だな、と思います。
あなたは、「戦士」ですか? それとも「村人」ですか? あるいは、その両方の心を持っているでしょうか? どんな答えであれ、あなたが選んだ道を、あなたらしく歩んでいけることを願っています。
フリーランサーや起業家は荒野の戦士みたいなものだと思っているので、彼らが互いを鼓舞したり発破をかけ合うのは良いと思います。でも「俺はずっと村人がいいんだ」と言っている人が、『戦士の掟』みたいなの押し付けられたら嫌じゃないかなと。
X (Twitter) – Mar 11, 2018
私個人への依頼について
私個人(トミナガハルキ)への依頼についてはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。広告デザイン制作、PR、執筆(書籍・記事)、SEOやサイト運営に関するアドバイス等を行なっています。リーズナブルにデザインを依頼したい
デザイン事務所AMIXの運営する【広告デザインのASOBOAD】ではパンフレットデザイン等をはじめ、各種広告デザインをリーズナブルな料金で行なっています。(※こちらは、主にスタッフがデザイン作成を行なっています。)