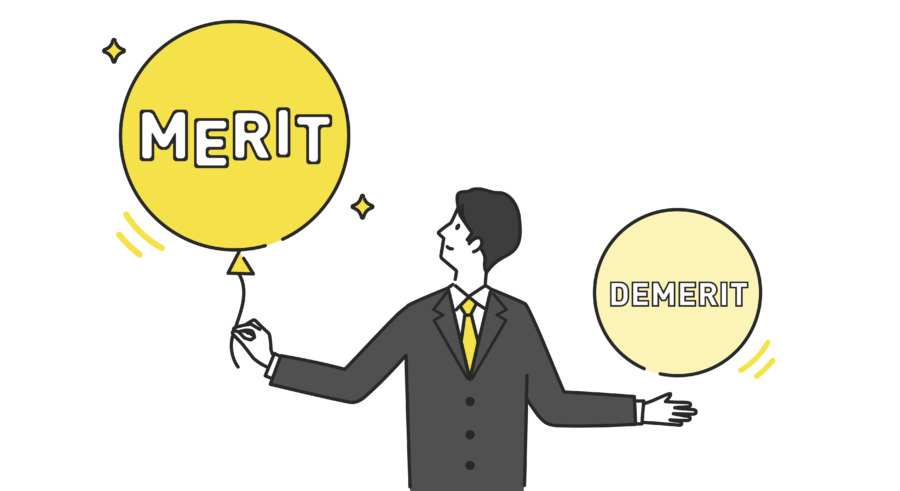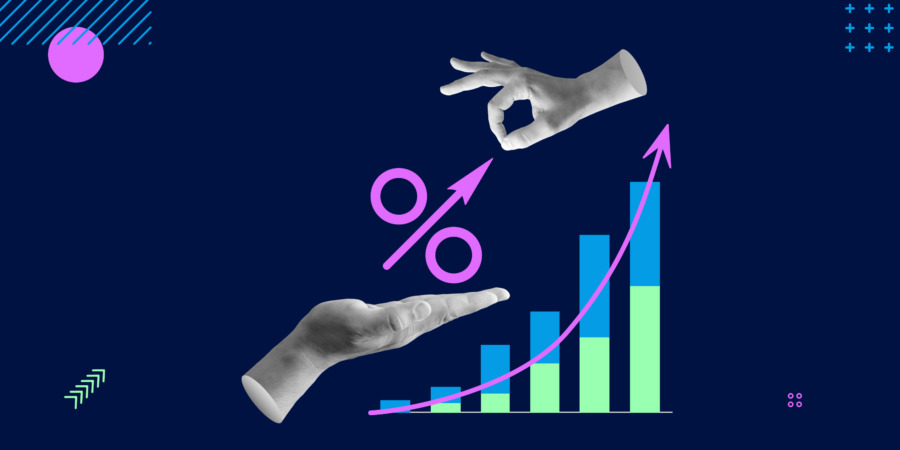「よし、新しいパンフレットを作るぞ!」そう意気込んだものの、最初の関門として立ちはだかるのが「社内稟議」。パンフレット制作担当者の皆さんの中には、この稟議を通すのに苦労したり、どうすれば上司や関係部署を説得できるのか頭を悩ませたりしている方も多いのではないでしょうか?
「本当に必要なの?」「費用対効果は?」「デザインがイマイチだったら…」
次々と投げかけられる疑問や不安の声に、自信を持って答えられず、企画自体が立ち消えになってしまう…なんてことも。
でも、安心してください。この記事では、そんなパンフレット制作担当者の皆さんの悩みを解決し、社内稟議をスムーズに通すための具体的な説得術と、そのまま使える資料作成のポイントを徹底解説します!
この記事を読めば、あなたも自信を持って稟議に臨み、想いの詰まったパンフレット制作への第一歩を踏み出せるはずです。
第1章:なぜパンフレット?今さら聞けない「作る意味」を再定義する

稟議を通す上で最も大切なのは、「なぜ今、パンフレットを作る必要があるのか?」という根本的な問いに、明確かつ力強く答えることです。デジタル全盛のこの時代だからこそ、パンフレットならではの価値を再認識し、その必要性を訴えましょう。
デジタル時代におけるパンフレットの価値とは?
ウェブサイトやSNSなど、デジタル媒体での情報発信が主流となっている現代において、あえて紙媒体であるパンフレットを作成する意義はどこにあるのでしょうか。
- 手元に残る安心感と信頼性: デジタル情報は流れていきやすいですが、パンフレットは物理的に手元に残ります。必要な時にすぐに見返せる利便性があり、手に取れる「モノ」としての存在感が、情報への信頼性を高める効果も期待できます。特に、高額な商品やサービス、BtoBの取引など、じっくりと比較検討したい場合には有効です。
- ターゲット顧客に合わせた情報提供: ウェブサイトのように網羅的な情報ではなく、特定のターゲット顧客層に向けて、本当に必要な情報だけを厳選して届けられるのがパンフレットの強みです。展示会や商談、店舗など、特定のタッチポイントで顧客に直接手渡すことで、より深いコミュニケーションのきっかけを作ることができます。
- ブランドの世界観を伝える重要なツール: 用紙の質感、デザイン、レイアウト、インクの乗り具合など、五感に訴えかける表現が可能なパンフレットは、企業のブランドイメージや世界観を効果的に伝えることができます。ウェブだけでは伝えきれない細やかなニュアンスや「らしさ」を表現し、顧客の記憶に残るブランド体験を提供します。
稟議で問われる「本当に必要?」に明確に答えるために
稟議の場で「本当にパンフレットが必要なのか?」と問われた際に、自信を持って「YES」と答えるためには、以下の点を明確にしておく必要があります。
- パンフレット制作の目的を明確にする:
何のためにパンフレットを作るのか?具体的な目的を定めましょう。
例:新規顧客獲得、既存顧客への新サービス紹介、採用活動における企業魅力の発信、イベントでのブランド認知向上など。 - ターゲット顧客は誰か?彼らはどんな情報を求めているか?:
誰に届けたいパンフレットなのか?そのターゲット顧客が、どんな情報を、どんな形で求めているのかを徹底的に考えます。ペルソナを設定するのも有効です。 - パンフレットが解決できる課題は何か?:
現状のビジネス課題の中で、パンフレットがどのような役割を果たし、何を解決できるのかを具体的に示します。
例:「ウェブサイトだけでは伝えきれない製品の魅力を補完し、商談時の成約率を向上させる」「展示会での名刺交換後のフォローアップツールとして活用し、見込み顧客の育成を強化する」など。
これらの点を整理することで、パンフレットの必要性に対する説得力が増し、稟議担当者も納得しやすくなります。
第2章:稟議担当者を納得させる!説得材料の見つけ方・伝え方

パンフレットの必要性を理解してもらえたとしても、次に待っているのは「効果」と「コスト」に関する厳しい追及です。ここでは、稟議担当者を納得させるための具体的な説得材料の見つけ方と、効果的な伝え方をご紹介します。
「効果が見えない」という反論を打ち破る!
パンフレットは、ウェブ広告のようにクリック数やコンバージョン率が明確に計測しづらいため、「効果が見えにくい」という印象を持たれがちです。この反論を打ち破るためには、効果を可視化する工夫と、具体的な事例を示すことが重要です。
- 効果測定の具体的な方法を提案する:
- QRコードの活用: パンフレット専用のウェブページや問い合わせフォームに誘導するQRコードを掲載し、そのアクセス数や問い合わせ数を計測する。
- 専用電話番号・クーポンコードの設置: パンフレット経由の問い合わせや来店を特定できるように、専用の電話番号や割引クーポンコードを記載する。
- アンケートの実施: パンフレットを受け取った顧客にアンケートを実施し、パンフレットの認知度や内容の満足度、行動喚起への影響などを調査する。
- 営業担当者へのヒアリング: 商談時にパンフレットをどのように活用し、顧客の反応はどうだったかなどを営業担当者から具体的にヒアリングする。
- 過去の成功事例や競合他社の活用事例を提示する:
社内外の成功事例は、効果をイメージさせる上で非常に有効です。
もし過去にパンフレットを制作した経験があれば、その時の反響や成果を具体的に示しましょう。
競合他社がどのようにパンフレットを活用し、成果を上げているかを調査し、提示するのも効果的です。「あの会社もやっているなら…」という心理が働くこともあります。 - デジタル施策との連携で相乗効果を生むことを説明する:
パンフレット単体での効果だけでなく、ウェブサイトやSNSなどのデジタル施策と連携させることで、より大きな相乗効果が期待できることをアピールします。
例:パンフレットで興味を持った顧客をQRコードで詳細なウェブページへ誘導し、そこで動画やお客様の声を見てもらう。その後、リターゲティング広告で再アプローチするなど。
「コストが高い」と言わせない!費用対効果の示し方
パンフレット制作には、デザイン費、印刷費など、ある程度のコストがかかります。稟議で「コストが高い」という意見が出た場合、単に「安くします」と言うのではなく、その投資に見合うだけの価値があることを示す必要があります。
- 単なる制作費ではなく、LTV(顧客生涯価値)やブランドイメージ向上への貢献度をアピール:
パンフレットによって獲得できた顧客が、長期的にどれだけの利益をもたらすのか(LTV)を試算したり、ブランドイメージの向上といった数値化しにくいが重要な価値への貢献を説明したりすることで、短期的なコストだけでなく、長期的なリターンに目を向けてもらいましょう。 - 複数の見積もりを取得し、価格の妥当性を示す:
複数の制作会社から見積もりを取り、比較検討した上で、提案しているプランが適正価格であることを客観的に示します。ただし、安さだけを追求するのではなく、品質やサポート体制とのバランスも考慮していることを伝えましょう。 - 予算内で最大限の効果を出すための工夫を説明する:
予算が限られている場合は、その範囲内で最大限の効果を出すための工夫を具体的に説明します。
例:用紙の選定、印刷部数の最適化、配布方法の見直し、デザインテンプレートの活用(※ただし、オリジナリティが求められる場合は注意が必要)など。
デザインは「好み」じゃない!客観的な根拠で説得する
パンフレットのデザインは、どうしても個人の好みが反映されやすい部分です。「このデザインは好きじゃない」「もっとこうしてほしい」といった主観的な意見に振り回されないためには、デザインの意図を客観的な根拠に基づいて説明することが不可欠です。
- ターゲット顧客のペルソナに基づいたデザインコンセプトを説明する:
「誰に」伝えたいのか、そのターゲット顧客の年齢、性別、嗜好、ライフスタイルなどを具体的に設定した「ペルソナ」を提示し、そのペルソナに響くデザインコンセプトであることを論理的に説明します。 - 企業のブランドイメージとの一貫性を強調する:
パンフレットのデザインが、企業のロゴ、コーポレートカラー、ウェブサイトのデザインなど、既存のブランド要素と一貫性があり、ブランドイメージを強化するものであることを説明します。 - 専門家の意見を取り入れる(プロのデザイナーに依頼するメリット):
「餅は餅屋」です。デザインの専門家であるプロのデザイナーに依頼することで、より訴求力の高い、洗練されたデザインが期待できることを伝えましょう。デザイン会社によっては、過去の制作実績や、デザインがもたらした具体的な効果(例:問い合わせ率の向上など)を提示できる場合もあります。
第3章:これで完璧!?社内稟議ウケする資料作成テンプレート

どんなに素晴らしいアイデアも、稟議書という形でまとめられなければ、承認を得ることはできません。ここでは、稟議担当者に「これならGOサインを出せる!」と思わせる、説得力のある稟議書の作成ポイントと、盛り込むべき項目をテンプレート形式でご紹介します。
稟議書作成の基本構成
一般的に、パンフレット制作の稟議書に盛り込むべき項目は以下の通りです。もちろん、会社の規定や文化によって必要な項目は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
| 必須項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 案件名 | パンフレット制作に関する稟議 |
| 2. 起案日・起案部署・起案者 | |
| 3. 目的 | なぜこのパンフレットを制作するのか?具体的に記載します。(例:新規顧客獲得、既存顧客への情報提供など) |
| 4. 背景・現状の課題 | パンフレット制作に至った背景、現状抱えている課題などを説明します。 |
| 5. パンフレットで実現したいこと | このパンフレットを通じて、どのような状態を実現したいのかを具体的に記述します。 |
| 6. ターゲット顧客 | 誰に向けたパンフレットなのか、具体的なターゲット像を明確にします。 |
| 7. 期待される効果 | パンフレット制作によって、どのような効果が期待できるのかを数値目標も交えて具体的に記述します。(例:問い合わせ数〇%増、成約率〇%向上、ブランド認知度〇%向上など) |
| 8. 制作概要 | サイズ、ページ数、色数、用紙、加工、部数、配布方法、デザインの方向性など、制作物の仕様を記載します。 |
| 9. スケジュール | 企画開始からデザイン制作、印刷、納品、配布開始までの具体的なスケジュールを提示します。 |
| 10. 予算 | デザイン費、印刷費、その他(撮影費、コピーライティング費など)の内訳と合計金額を明記します。 |
| 11. 費用対効果 | 投資する予算に対して、どのようなリターンが見込めるのかを具体的に説明します。 |
| 12. 制作体制 | 社内の担当者、外部委託先(制作会社名など)を記載します。 |
| 13. 代替案との比較(任意) | パンフレット以外の手段(例:ウェブ広告強化など)と比較し、なぜパンフレットが最適なのかを説明します。 |
| 14. 添付資料 | 見積書、デザイン案(ラフでも可)、参考資料などがあれば添付します。 |
各項目の書き方ポイントと例文
- 「目的」:誰に何を伝え、どうなってほしいのかを具体的に
NG例:営業力強化のため。
OK例:〇〇業界の新規開拓を目指し、当社の主力製品である△△の機能と導入事例を分かりやすく伝え、見込み顧客からの問い合わせを月間10件獲得することを目的とします。 - 「期待効果」:数値目標も交え、具体的に記述する
NG例:売上アップに貢献する。
OK例:本パンフレット導入後3ヶ月で、商談時の成約率を現状から5%向上させることを目指します。また、ウェブサイトへのアクセス数が月間〇〇PV増加し、ブランド認知度の向上に貢献すると期待されます。 - 「予算」:内訳を明確にし、投資としてのリターンを強調する
デザイン費、印刷費、その他諸経費の内訳を明確に記載し、なぜその金額が必要なのかを説明します。単なるコストではなく、将来の利益を生み出すための「投資」であることを意識して記述しましょう。 - デザイン案がある場合は、コンセプトと合わせて提示する
まだ具体的なデザイン案がない場合でも、どのような方向性のデザインを考えているのか、参考となるイメージやキーワードを伝えられると良いでしょう。もしラフ案などがあれば、それも添付資料として提出します。
NG例:これでは通らない!稟議で避けたい表現や内容
- 抽象的な表現や精神論に終始する: 「頑張ります」「顧客満足度向上を目指します」といった具体性のない言葉は避けましょう。
- 根拠のない自信や希望的観測: 「必ず成功します」「おそらく〇〇になるでしょう」など、客観的なデータや分析に基づかない表現は説得力に欠けます。
- 丸投げ感のある提案: 「詳細は専門業者にお任せします」といった姿勢ではなく、主体的にプロジェクトを推進する意志を示すことが大切です。
- 予算やスケジュールが曖昧: 具体的な数値や期日が不明確だと、計画性のなさを指摘されます。
- リスクや懸念事項を隠す: 想定されるリスクや課題についても触れ、それに対する対策を提示することで、誠実な印象を与え、信頼を得やすくなります。
第4章:稟議を有利に進める!社内調整と根回しの極意

どんなに素晴らしい稟議書を作成しても、それだけでは稟議がスムーズに通るとは限りません。稟議を有利に進めるためには、事前の社内調整、いわゆる「根回し」が非常に重要になってきます。
誰を味方につけるべき?キーパーソンを見極める
まず、稟議の承認プロセスに関わるキーパーソン(直属の上司、関連部署の責任者、役員など)を特定します。そして、それぞれのキーパーソンがどのような情報を重視し、どのような点に懸念を抱きそうかを事前に把握しておきましょう。
反対意見を想定し、事前に潰しておく
稟議を提出する前に、キーパーソンや関係者に個別に相談し、意見を聞いておくことが有効です。この段階で出てきた疑問や反対意見に対して、真摯に耳を傾け、事前に回答を用意しておくことで、稟議の場で不意打ちを食らうことを避けられます。
例えば、営業部門からは「もっと現場で使いやすい情報が欲しい」、経理部門からは「コストをもう少し抑えられないか」といった意見が出るかもしれません。これらの意見を事前に吸い上げ、可能な範囲で稟議書や企画内容に反映させることで、関係者を「巻き込む」形を作ることができます。
関係部署との連携:巻き込み型のパンフレット制作
パンフレット制作は、決して担当者一人の仕事ではありません。関係部署と積極的に連携し、彼らの意見やニーズを反映させることで、より実用的で効果の高いパンフレットが完成し、稟議も通りやすくなります。
- 営業部門: パンフレットを実際に使用するのは営業担当者であることが多いでしょう。彼らが顧客に説明しやすい情報、アピールしたいポイントなどをヒアリングし、パンフレットに盛り込みましょう。完成後も、パンフレットの活用方法について研修を行うなど、連携を密にすることが重要です。
- 広報・マーケティング部門: 企業のブランド戦略や他のマーケティング施策との整合性を取るために、広報・マーケティング部門との連携は不可欠です。パンフレットのデザインやメッセージが、企業全体のブランドイメージと合致しているか、他の施策と相乗効果を生み出せるかなどを共に検討しましょう。
- 経営層: 最終的な承認者である経営層には、パンフレット制作が企業の経営課題の解決や事業目標の達成にどのように貢献できるのか、という視点で説明することが重要です。短期的な成果だけでなく、中長期的なビジョンとの繋がりを示すことで、より大きな納得感を得られます。
熱意とロジックで、最後の一押し!
最終的には、あなたの「このパンフレットで会社を良くしたい!」という熱意が、稟議を動かす最後の一押しになることもあります。しかし、熱意だけでは空回りしてしまいます。ここまで準備してきた客観的なデータ、論理的な説明、そして関係部署との連携という土台があってこそ、あなたの熱意は相手に響くのです。
自信を持って、あなたの言葉で、パンフレット制作への想いを伝えましょう。
第5章:もっと伝わるパンフレットへ!制作会社選びも稟議のポイント
無事に社内稟議を通過したら、いよいよパンフレット制作の具体的なステップに進みます。しかし、パンフレット制作は「作って終わり」ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、信頼できる制作会社をパートナーとして選ぶことが非常に重要です。実は、この「どんな会社に依頼するのか」という点も、稟議の段階で説明を求められることがあります。
パンフレット制作はゴールではなくスタート
素晴らしいパンフレットが完成しても、それがターゲット顧客の手に渡り、心を動かし、行動を促さなければ意味がありません。制作会社を選ぶ際には、単にデザインが美しい、価格が安いというだけでなく、あなたの会社の目的や課題を深く理解し、その解決に貢献してくれるパートナーシップを築けるかどうかを見極めることが大切です。
「想いをカタチに」してくれるパートナー選びの重要性
では、どのような視点で制作会社を選べば良いのでしょうか?
- 実績だけでなく、コミュニケーションの取りやすさ、提案力も重視:
過去の制作実績はもちろん重要ですが、それ以上に、担当者とのコミュニケーションがスムーズに進むか、こちらの意図を的確に汲み取ってくれるか、そして期待以上の提案をしてくれるか、といった点も重視しましょう。制作プロセスは、二人三脚で進めていくものです。 - デザイン力はもちろん、マーケティング視点も持っているか:
見た目の美しさだけでなく、誰に何を伝え、どう行動してほしいのか、というマーケティング視点に基づいた情報設計やデザインができる会社を選びましょう。ターゲット顧客のインサイトを捉え、効果的な訴求ができるパンフレット作りをサポートしてくれるはずです。
【ASOBOADの紹介】私たちのパンフレット制作サービスが選ばれる理由
ここで少し、私たちのパンフレット制作サービスについてご紹介させてください。私たちASOBOADは、「デザインをもっと身近に」をモットーに、単に見た目が良いだけでなく、コストを意識したパンフレット制作を追求しています。
もし、パンフレット制作のパートナー選びでお悩みでしたら、ぜひ一度ASOBOADにご相談ください。あなたの会社の「想い」を伝えるパンフレットを一緒に作り上げていきましょう。
まとめ
パンフレット制作における最初の、そして最大の難関とも言える「社内稟議」。しかし、この記事でご紹介した説得術や資料作成のポイントを押さえ、しっかりと準備をすれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
大切なのは、パンフレットを作る「目的」を明確にし、その「効果」を具体的に示し、関係者を「巻き込みながら」進めていくことです。そして何よりも、あなたの「このパンフレットでビジネスを加速させたい!」という熱意が、周囲を動かす原動力となります。
この記事が、あなたのパンフレット制作プロジェクトを成功へと導く一助となれば幸いです。パンフレットを通じて、企業の想いを届け、顧客との新たな出会いを創造し、ビジネスをさらに発展させていきましょう。
ASOBOADは、そんなあなたのパンフレット制作を、リーズナブルにサポートさせていただきます。パンフレットに関するご相談や、具体的な制作に関するお見積もりなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。
サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧